
新築の外構工事は何から始める?計画から完成までの全7ステップ
新築の家づくりも大詰め、でも「外構工事って何から始めればいいの?」と悩んでいませんか。 費用やスケジュールが分からず、せっかくのマイホームで失敗したくない、という気持ちは皆同じです。 実は、外構工事を成功させるには、計画から完成までの流れを7つのステップで正しく理解することが鍵です。 この記事では、外構工事を始めるべき最適なタイミングから業者選び、完成までの具体的な全7ステップを徹底解説。 最後まで読めば、もう迷うことなく理想の外構づくりの第一歩を踏み出せます。
目次
この記事のポイント
- 外構工事を始めるべきベストなタイミングがわかる
- 計画から完成までの具体的な7ステップを理解できる
- 外構工事の費用相場や予算50万円でできるプラン例がわかる
- 失敗しないための注意点や費用を抑えるコツがわかる
【いつから動くべき?】新築の外構工事を始めるベストなタイミング

新築の外構工事、いつから考えればいいか悩みますよね。
実は最適なタイミングがあります。この記事でスッキリ解決しましょう。
- なぜ家の設計段階から外構を考えるべきなの?
- 遅すぎるとどうなる?計画が遅れた場合のリスク
まずは計画を始めるべき理由から見ていきましょう。
なぜ家の設計段階から外構を考えるべきなの?
結論から言うと、外構工事の計画は家の間取りが決まった段階でスタートするのが理想的です。
なぜなら、家の設計と外構デザインは、暮らしやすさに直結する部分で密接に関わっているからです。
例えば、リビングに大きな窓を設置しても、その目の前がお隣の窓や道路だったら、視線が気になってカーテンを開けられないかもしれません。
家の設計段階で外構計画も進めていれば、窓の位置に合わせて目隠しフェンスや植栽の計画を立てることができます。
また、エアコンの室外機や給湯器、水道メーターなどの位置も重要です。
これらの設備は一度設置すると移動が難しく、後から「ここにウッドデッキを作りたかったのに…」などと後悔する原因になりかねません。
さらに、駐車場から玄関、勝手口からゴミ置き場への動線も、生活を快適にする工夫も、家と外構を一体で考えることで最適化できます。
予算面でも、家のローンに外構費用を組み込める場合があるため、早い段階で総額を把握しておくことが大切です。
遅すぎるとどうなる?計画が遅れた場合のリスク
もし外構計画を後回しにして、家の完成が近づいてから慌てて始めると、いくつかのリスクが生じる可能性があります。
最も大きな問題は、費用が割高になったり、理想のデザインを諦めなければならなくなったりすることです。
例えば、後から駐車場にカーポートを設置しようとした際に、地中に水道管が通っていることが判明し、追加の工事費用が発生するケースがあります。
また、入居が迫る中で急いで業者を探すと、複数の業者を比較検討する時間がありません。
その結果、相場より高い金額で契約してしまったり、デザインの提案力が高くない業者に依頼してしまったりするリスクも高まります。
計画が遅れた場合のリスクをまとめると、以下のようになります。
リスクの種類 | 具体的な内容 |
費用面のリスク | ・地面の掘り返しなど二度手間な工事が発生し、費用が割高になる ・住宅ローンに外構費用を組み込めず、資金計画が狂う |
デザイン面のリスク | ・設備の配置が原因で、理想のウッドデッキや庭のレイアウトを諦めることになる ・家の外観と外構のデザインに統一感がなくなる |
生活面のリスク | ・駐車場が未舗装のまま入居し、雨の日に車や玄関が泥だらけになる ・隣家からの視線が気になり、落ち着いて生活できない |
業者選びのリスク | ・時間的な焦りから、業者を十分に比較検討できずに契約してしまう |
こうした事態を避けるため、外構工事は「家が建ってから」ではなく「家と一緒に」計画し、早めに準備することが成功の鍵です。
新築の外構工事、何から始める?相談から完成までの基本的な流れ

実際に何から手をつけるべきか、工事全体の流れが気になりますね。
外構工事の流れは大きく4つのステップに分けられます。順番に見ていきましょう。
- ステップ1:情報収集とイメージ固め
- ステップ2:業者探しと相談・相見積もり
- ステップ3:プランニングと契約
- ステップ4:着工から完成・引き渡し
まずは最初のステップから具体的に解説します。
ステップ1:情報収集とイメージ固め
外構工事の計画における最初のステップは、自分たちが「どんな外構にしたいのか」というイメージを具体的にすることです。
まずはSNSやインターネット、住宅雑誌などを活用して、好みのデザインの写真や事例をたくさん集めてみましょう。
「ナチュラルな雰囲気の庭」「シンプルモダンな駐車場」といったキーワードで検索すると、参考になる画像がたくさん見つかります。
気に入った写真を集めていくうちに、自分たちの好みのテイストやスタイルがだんだんと明確になってくるはずです。
写真が集まったら、家族で話し合いながら、「絶対に譲れない条件」と「できれば実現したい要望」をリストアップすることをおすすめします。
例えば、「車は2台分、絶対に必要」「夏に子どもが水遊びできるスペースが欲しい」など、具体的な要望を整理しておくといいでしょう。
この後の業者との打ち合わせが非常にスムーズに進みます。
ステップ2:業者探しと相談・相見積もり
理想の外構のイメージが固まったら、次に工事を依頼する業者を探すステップへと進みます。
外構工事の依頼先には、家を建てたハウスメーカーや工務店、あるいは外構・エクステリアの専門業者といった選択肢があります。
ここで非常に重要なポイントが、必ず2〜3社程度から「相見積もり」を取ることです。
相見積もりとは、同じ要望を複数の業者に伝えて、それぞれからデザインプランと見積書を提出してもらうことを指します。
相見積もりを取ることで、費用の適正価格を把握できるだけでなく、各社のデザインの提案力や担当者の対応、人柄などを比較検討できます。
手間はかかりますが、このひと手間が、満足のいく業者選びと後悔のない外構工事に繋がるのです。
相談の際には、ステップ1で集めた写真や要望リストを提示すると、自分たちのイメージをより正確に伝えられます。
ステップ3:プランニングと契約
複数の業者からの提案と見積もりをじっくり比較し、最も信頼できると感じた1社に絞り込みます。
業者を決めたら、そこからさらに詳細なプランニングの打ち合わせを重ねていくことになります。
この段階では、図面をもとに、使用する素材や色、フェンスのデザイン、植栽の種類など、詳細な仕様を決めていきます。
少しでも疑問や不安に思うことがあれば、遠慮せずに質問し、すべて解消しておくことが大切です。
最終的なプランと見積金額に双方が納得したら、工事請負契約を結びます。
契約書にサインする前には、工事の期間、費用の支払い条件、そして工事後の保証内容など、記載されている項目を隅々まで確認するようにしましょう。
ステップ4:着工から完成・引き渡し
契約が無事に完了すると、いよいよ実際の工事が始まります。
工事期間は、その規模や内容、天候によって変動しますが、一般的には数週間から2ヶ月程度が目安です。
工事前の挨拶は業者が行うのが通例ですが、施主からも一言挨拶しておくと、ご近所付き合いがより円滑になります。
工事期間中も、可能であれば時々現場を訪れて、作業の進捗状況を確認すると安心です。
すべての工事が完了したら、業者担当者の立ち会いのもと、完成した外構の最終チェックをします。
図面通りに仕上がっているか、フェンスに傷はないか、門扉はスムーズに開閉するかなどを細かく確認してください。
すべて問題ないことが確認できれば、無事に引き渡しとなり、理想の外構が完成します。
【種類別】新築の外構工事にかかる費用相場を徹底解説

外構工事の計画で一番気になるのは、やはり費用がどれくらいかかるかですよね。
ここでは主要な工事の種類別に、費用の目安を分かりやすく解説しますので、予算を考える際の参考にしてください。
- 駐車場・カーポートの費用相場
- 玄関アプローチ・門まわりの費用相場
- フェンス・塀の費用相場
- 庭・ウッドデッキの費用相場
まずは毎日使うことになる、駐車場の費用から見ていきましょう。
駐車場・カーポートの費用相場
駐車スペースの工事は、地面の仕上げ方によって費用が大きく異なります。最も一般的なのは、耐久性が高くメンテナンスも楽なコンクリート仕上げです。
仕上げの種類 | 費用相場(車1台分 / 約15㎡) | 特徴 |
コンクリート | 10万円 ~ 20万円 | 最も一般的で耐久性が高い。雑草の心配もない。 |
砂利敷き | 3万円 ~ 6万円 | 最も安価。防犯効果も期待できるが、雑草対策が必要。 |
アスファルト | 8万円 ~ 15万円 | コンクリートよりやや安価だが、夏場に表面が高温になる。 |
また、雨や鳥のフン、夏の強い日差しから車を守るカーポートを設置する場合は、別途費用がかかります。
一般的な片側支持タイプの1台用カーポートであれば、工事費込みで15万円〜30万円程度が相場です。
玄関アプローチ・門まわりの費用相場
玄関アプローチや門まわりは「家の顔」とも言える重要な部分です。使う素材によって費用だけでなく、家全体の印象が大きく変わります。
玄関アプローチの費用相場
- コンクリート仕上げ:5万円 〜 10万円(シンプルで機能的)
- タイル貼り:10万円 〜 20万円(高級感があり掃除もしやすい)
- レンガ・自然石:15万円 〜 30万円(温かみがあり、洋風のデザインに合う)
門まわりには、表札やポスト、インターホンを取り付ける「門柱」や、道路からの出入り口となる「門扉」の設置が含まれます。
シンプルな機能が一体になった機能門柱であれば5万円〜15万円程度、タイルや塗り壁で造作するおしゃれな門柱は20万円以上かかることもあります。
アルミ製の門扉は5万円〜15万円程度が一般的な価格帯です。
フェンス・塀の費用相場
お隣との境界を明確にしたり、道路からの視線を遮ってプライバシーを守ったりするためにフェンスや塀を設置します。
費用は素材と設置する長さによって決まるため、1メートルあたりの単価で考えるのが分かりやすいでしょう。
フェンスの種類 | 費用相場(1メートルあたり) | 主な用途・特徴 |
メッシュフェンス | 5,000円 ~ 1万円 | 最も安価。風通しが良く、主に隣地との境界に使われる。 |
アルミ形材フェンス | 1万円 ~ 3万円 | デザインが豊富で最も一般的。目隠しタイプも人気。 |
ウッド調フェンス | 2万円 ~ 4万円 | ナチュラルな雰囲気。腐食しにくい樹脂製が主流。 |
ブロック塀 | 1.5万円 ~ 3万円 | プライバシー確保に最適。基礎工事が必要なため高価になりやすい。 |
どの程度の目隠しが必要か、家のデザインとの調和はどうか、といった観点から最適なものを選ぶことが大切です。
庭・ウッドデッキの費用相場
お庭をどのように使うかによって、工事の内容は大きく変わります。
子どもやペットが走り回れるように芝生を敷いたり、リビングの延長として使えるウッドデッキを設置したりするのが人気です。
庭まわりの費用相場
- 天然芝:1㎡あたり3,000円 〜 5,000円(初期費用は安いが、定期的な手入れが必要)
- 人工芝:1㎡あたり7,000円 〜 1万円(手入れ不要で一年中緑を楽しめる)
- ウッドデッキ:20万円 〜 60万円(約6畳の場合。材質により価格が大きく変動)
- 植栽(シンボルツリー):3万円 〜 10万円(木の高さや種類による)
ウッドデッキは、比較的安価な天然木(ソフトウッド)か、高価ですが耐久性の高い樹脂木や天然木(ハードウッド)かによって価格が大きく変動します。
メンテナンスの手間や予算を考慮して選びましょう。
これらの費用はあくまで目安です。土地の状態や選ぶ製品のグレードによって金額は変わるため、正確な費用は必ず業者からの見積もりで確認してください。
【予算50万円でどこまでできる?】価格帯別の外構工事プラン例

おおよその費用相場が分かっても、実際の予算でどこまでの工事が可能なのか、具体的にイメージするのは難しいですよね。
ここでは予算別に実現可能なプランの組み合わせ例をシミュレーションしてみましょう。ご自身の予算感と照らし合わせてみてください。
- 予算50万円で実現できる工事の組み合わせ例
- 予算100万円で実現できる工事の組み合わせ例
- 予算150万円以上で実現できる工事の組み合わせ例
まずは最もコンパクトな50万円のプランから見ていきましょう。
予算50万円で実現できる工事の組み合わせ例
【こんな人におすすめ】
- とにかく初期費用を抑えたい
- まずは生活に最低限必要な部分だけを整えたい
- DIYも取り入れつつ、少しずつ理想の外構を作っていきたい
予算50万円のプランは、生活に必須となる機能性を最優先した、シンプルでコンパクトな外構を目指すプランです。
見た目のデザイン性よりも、まずは駐車場や玄関まわりなど、毎日の生活で必ず使う部分を整備することに重点を置きます。
【工事プランの組み合わせ例】
- 駐車場:車1台分のコンクリート舗装
- アプローチ:砂利敷き、またはシンプルなコンクリートの通路
- 門柱:ポスト・表札・インターホンが一体となった機能門柱
- 境界:隣地との境界など、必要な箇所にのみ安価なメッシュフェンスを設置
- 庭:整地のみ、または防草シートと砂利敷きで雑草対策
このプランでは、庭の芝生やウッドデッキなどは含めず、将来的に予算ができたときに追加工事することを視野に入れます。
まずは暮らしの基盤を整え、その後自分たちの手で少しずつ手を加えていく楽しみも生まれるプランです。
予算100万円で実現できる工事の組み合わせ例
【こんな人におすすめ】
- 新築の外構として一般的なレベルに整えたい
- 機能性に加えて、ある程度の見栄えやデザイン性も欲しい
- 暮らしやすさを重視したい
予算100万円は、新築の外構工事で最も多い価格帯です。
生活に必要な機能を一通り網羅しつつ、デザイン性も少し加えられるようになり、満足度の高い外構を実現できます。
【工事プランの組み合わせ例】
- 駐車場:車2台分のコンクリート舗装
- アプローチ:タイル貼りやレンガ敷きなど、デザイン性のある舗装
- 門柱:シンプルな機能門柱、またはコンパクトな塗り壁の造作門柱
- 境界:道路に面した部分や隣地との境界に、目隠し機能のあるアルミ形材フェンスを設置
- その他:小さなシンボルツリーの植栽や、玄関まわりの花壇の設置
この価格帯になると、アプローチの素材を選んだり、ある程度の範囲をフェンスで囲ったりと、選択肢が広がります。
暮らしやすさと見た目のバランスが良く、多くの方にとって基準となるプランです。
予算150万円以上で実現できる工事の組み合わせ例
【こんな人におすすめ】
- 機能性はもちろん、デザインにもしっかりこだわりたい
- ウッドデッキやカーポートなど、プラスアルファの設備が欲しい
- オリジナリティのある、自慢できる外構にしたい
予算150万円以上になると、外構全体をトータルコーディネートし、デザイン性に優れたこだわりの空間を作ることが可能になります。
生活の質を高めるための、プラスアルファの設備も導入できるでしょう。
【工事プランの組み合わせ例】
- 駐車場:車2台分のコンクリート舗装 + カーポートの設置
- アプローチ:自然石を使った高級感のあるデザイン
- 門柱・門扉:オリジナルの造作門柱と、デザイン性の高いアルミ鋳物の門扉
- 境界:建物全体を囲うように、プライバシー性の高い目隠しフェンスを設置
- 庭:リビングと繋がるウッドデッキやタイルテラスの設置、庭全体の芝生、複数の植栽、夜間を彩るガーデンライトなど
まさに「理想のマイホーム」を完成させるための、こだわりのプランです。
家全体の価値をさらに高めるような、オリジナリティあふれる外構を実現できます。
予算 | 50万円プラン | 100万円プラン | 150万円以上プラン |
コンセプト | 機能性最優先 | バランス重視 | こだわり・デザイン性重視 |
駐車場 | 1台分コンクリート | 2台分コンクリート | 2台分コンクリート+カーポート |
アプローチ | シンプルなコンクリート | タイルやレンガ | 自然石など |
フェンス | 部分的なメッシュフェンス | アルミ形材フェンス | 全体を囲う目隠しフェンス |
庭 | 整地のみ | 簡単な植栽・芝生 | ウッドデッキ、ライティング等 |
新築の外構工事はどこに頼む?業者選びの3つの選択肢とポイント

業者選びは外構工事の成功を左右する、非常に重要なポイントです。
主な依頼先は2つあります。それぞれの特徴を知り、ご自身に合った最適な選択をしましょう。
- ハウスメーカー・工務店に頼むメリット・デメリット
- 外構・エクステリア専門業者に頼むメリット・デメリット
- 結局どちらがおすすめ?何を基準に選ぶべきか
まずは、家を建ててもらったハウスメーカーにそのまま依頼するケースから見ていきましょう。
ハウスメーカー・工務店に頼むメリット・デメリット
家の建築を依頼したハウスメーカーや工務店に、外構工事もまとめてお願いする方法です。
多くの人がまず検討する選択肢ですが、メリットとデメリットの両方を理解しておくことが大切です。
【メリット】
家の打ち合わせの延長で外構の話を進められ、担当者も同じなので窓口が一本化され、手間がかからないのが一番のメリットです。
また、外構費用を住宅ローンに組み込みやすいため、資金計画が立てやすい点も魅力です。
家の設計と同時に外構を考えることで、建物とデザインに統一感のある仕上がりになります。
【デメリット】
一方で、費用が割高になる傾向がある点はデメリットと言えます。
ハウスメーカーは外構工事を下請け業者に発注することがほとんどで、その際に中間マージンが発生するためです。
また、提携している業者が限られているため、デザインの提案が画一的になったり、専門業者ほど選択肢が多くなかったりする場合もあります。
外構・エクステリア専門業者に頼むメリット・デメリット
外構やエクステリアの設計・施工を専門に行っている業者に、直接工事を依頼する方法です。自分で業者を探す手間はかかりますが、多くのメリットがあります。
【メリット】
専門業者に直接依頼するため中間マージンが発生せず、費用を抑えられる可能性が高いのが最大のメリットです。
また、外構に関する知識や施工経験が豊富なため、デザインの引き出しが多く、提案力が高いことも特徴です。
素材選びからメンテナンスの方法まで、プロならではの専門的なアドバイスを受けながら、こだわりのあるオリジナリティの高い外構を実現できます。
【デメリット】
デメリットは、数多くある業者の中から信頼できる一社を自分で見つけなければならない点です。
業者によってデザインのセンスや技術力に差があるため、しっかりと見極める必要があります。
また、ハウスメーカーと提携していない場合、外構費用を住宅ローンに組み込めず、別途現金やリフォームローンなどを用意する必要があるかもしれません。
結局どちらがおすすめ?何を基準に選ぶべきか
どちらの業者を選ぶべきか、それぞれの特徴を表で比較してみましょう。
ハウスメーカー・工務店 | 外構・エクステリア専門業者 | |
費用 | 割高になりやすい | 抑えやすい |
デザイン性 | 標準的・統一感が出やすい | 自由度・専門性が高い |
手間 | 少ない(窓口が一本) | 多い(自分で探す必要あり) |
ローン | 住宅ローンに組み込みやすい | 別途ローンが必要な場合も |
結論として、あなたが何を最も重視するかによっておすすめの依頼先は変わります。
【ハウスメーカーがおすすめな人】
- とにかく手間をかけたくない、打ち合わせをまとめて済ませたい方
- 外構費用を必ず住宅ローンに含めたい方
- 外構に強いこだわりはなく、標準的な仕上がりで満足な方
【専門業者がおすすめな人】
- 少しでも費用を抑えたい、コストパフォーマンスを重視する方
- デザインにこだわりたい、オリジナリティを追求したい方
- 自分で情報収集をしたり、業者を探したりする手間を惜しまない方
後悔しないための方法としては、まずハウスメーカーから外構プランの提案と見積をもらい、それを基準に専門業者2~3社程度に相見積もりを依頼することです。
そうすることで、費用とデザインの両方を比較検討でき、心から納得できる業者を選べるでしょう。
おしゃれな新築外構を実現するデザインのコツ

せっかくの新築ですから、外構もおしゃれで素敵な空間にしたいですよね。
いくつかのデザインのコツを押さえるだけで、外構は見違えるほど素敵になります。誰でも実践できるポイントを紹介します。
- 家の外観とテイストを合わせる「統一感」
- プライバシーと開放感を両立させる「セミクローズド外構」
- 夜の雰囲気を演出する「ライティング(照明)」
まずは最も基本となる、建物との統一感から解説します。
家の外観とテイストを合わせる「統一感」
おしゃれな外構デザインで最も重要なポイントは、建物との「統一感」です。
外構だけが独立して存在するのではなく、家の一部として調和しているかどうかが、全体の印象を大きく左右します。
まずは、ご自身の家の外観デザインがどのようなテイストかを確認してみましょう。
例えば、シンプルモダン、ナチュラル、南欧風、和モダンなど、様々なスタイルがあります。
そのテイストに合わせて、外構で使う素材や色、デザインの方向性を決めていくのが基本です。
- シンプルモダンな家なら…
コンクリートや金属、ガラスといった無機質でシャープな素材が似合います。色は白・黒・グレーといったモノトーンを基調に、直線的なデザインでまとめると、洗練された印象になります。
- ナチュラルテイストの家なら…
ウッドフェンスや枕木、レンガといった自然素材を積極的に取り入れましょう。植栽の緑も重要な要素です。曲線的なアプローチなどにすると、より柔らかく温かみのある雰囲気を作り出せます。
個々のパーツで考えるのではなく、家と庭全体を一つの作品としてトータルコーディネートする意識が、統一感を出す鍵です。
プライバシーと開放感を両立させる「セミクローズド外構」
外構のスタイルは、敷地の囲い方によって大きく3種類に分けられます。
外構スタイル | 特徴 | メリット | デメリット |
オープン外構 | 門や塀で敷地を囲わない | 開放感がある、費用が安い | プライバシー確保が難しい |
クローズド外構 | 高い塀や門で敷地を囲う | プライバシーを確保しやすい | 圧迫感がある、費用が高い |
セミクローズド外構 | 上記2つの中間 | 開放感とプライバシーを両立 | バランスの設計が重要 |
現代の住宅で主流となっているのが、この3つ目の「セミクローズド外構」です。
敷地全体を完全に閉ざすのではなく、「隠すところ」と「見せるところ」を分けることで、プライバシーを守りつつも、圧迫感のないおしゃれな空間を演出できます。
例えば、道路からの視線が気になるリビングの前だけは背の高い目隠しフェンスを設置し、玄関まわりは低い植栽にして開放感を出す、といった工夫が可能です。
完全に視線を遮断しない格子状のフェンス(ルーバーフェンス)などを活用するのも、圧迫感を和らげるのに効果的です。
この「抜け感」のバランスが、おしゃれな外構を実現するポイントになります。
夜の雰囲気を演出する「ライティング(照明)」
見落とされがちですが、外構の印象を劇的に変えるのが「ライティング(照明)」です。
適切に照明を配置することで、夜の外観は昼間とは全く違う、幻想的で高級感のある表情を見せてくれます。
ライティングには、主に3つの役割があります。
- 防犯性:暗がりをなくすことで、不審者が隠れる場所をなくし、侵入を防ぎます。
- 安全性:玄関までのアプローチや階段の足元を照らし、夜間のつまずきや転倒を防ぎます。
- 演出性:シンボルツリーを下から照らし上げたり(アップライト)、壁に光を当てて美しい陰影を作ったりすることで、ムードのある空間を創出します。
門柱灯や足元を照らすフットライト、植栽を照らすスポットライトなどを効果的に組み合わせることで、費用対効果が非常に高いデザインが実現できます。
最近のガーデンライトはほとんどがLEDなので、電気代を心配する必要もほとんどありません。
外構計画の段階で、ぜひ照明計画も一緒に検討することをおすすめします。
【失敗談から学ぶ】新築の外構工事で後悔しないための注意点

「住んでみたら、なんだか使いにくい…」「こんなはずじゃなかった…」という後悔は、絶対にしたくありませんよね。
ここでは、先輩たちが経験した外構工事のよくある失敗例とその対策をご紹介します。
同じ失敗を繰り返さないためのヒントを学んでいきましょう。
- 駐車スペースが狭くて使いにくい
- お隣さんからの視線が気になる
- 雨の日に水たまりができてしまう
- コンセントや水道がなくて不便
まずは、毎日の生活に直結する駐車場の失敗例から見ていきます。
駐車スペースが狭くて使いにくい
【よくある失敗談】
「車のサイズぴったりで駐車場を設計したら、ドアを開けるときに隣の車や壁にぶつけそうでヒヤヒヤする」
「自転車を置くスペースまで考えていなくて、結局車が出しにくい場所に置くことになってしまった…」
これは、車の幅と長さだけでスペースを考えてしまい、人の乗り降りや、荷物の出し入れなどの「動作」のスペースを考慮しなかったために起こる失敗です。
【対策】
駐車スペースは、車の寸法に加えて、左右にそれぞれ60cm以上、前後に50cm以上の余裕を持たせるのが理想です。
ドアを全開にしても安心なスペースを確保することで、毎日の乗り降りがストレスフリーになります。
また、将来の車の買い替えや、子どもの成長に伴う自転車の増加なども見越して、少し広すぎるくらいに計画しておくことをおすすめします。
お隣さんからの視線が気になる
【よくある失敗談】
「リビングの大きな窓から光を取り込めるようにしたのに、お隣の窓や道路を歩く人の視線が気になって、結局一日中カーテンを閉めっぱなし…」
図面の上だけでプランを考えていると、実際の土地での隣家や道路との位置関係、高低差などを見落としてしまいがちです。
【対策】
家の間取りが決まったら、必ず一度は建設予定地に立って、周囲からの視線を確認しましょう。
特にリビングや浴室など、プライバシーを確保したい部屋の窓が、どこから見えそうかをご自身の目でチェックすることが重要です。
その上で、視線が気になる箇所には目隠しフェンスを設置したり、植栽を配置したりする計画を立てましょう。
業者にも「この窓からの視線が気になる」と具体的に伝えることで、最適な解決策を提案してもらえます。
雨の日に水たまりができてしまう
【よくある失敗談】
「雨が降ると、駐車場や玄関アプローチに大きな水たまりができてしまう。車から降りる時に靴が濡れるし、いつまでもジメジメしてコケが生えてきた…」
この原因は、地面の「水勾配(みずこうばい)」が適切に設定されていないことにあります。
水勾配とは、雨水などをスムーズに排水溝へと流すための、ごくわずかな傾斜のことです。
【対策】
通常、プロの業者は必ずこの水勾配を計算して施工しますが、念のためプランニングの段階で「水はけ対策はどのようにしますか?」と確認しておくと安心です。
また、地面をコンクリートで覆う面積が広い場合は、排水用の溝を設けたり、水を通しやすい「透水性コンクリート」といった素材を使ったりする方法も有効です。
コンセントや水道がなくて不便
【よくある失敗談】
「庭でバーベキューしようとしたら電源がなくて、家の中から長い延長コードを引いてきた」「洗車や庭の水やりがしたいのに、外に水道がなくてとても不便…」
これは、家の中のことばかり考えてしまい、屋外での電気や水の使い方を具体的にイメージしていなかったために起こる、非常によくある失敗です。
【対策】
外構計画の段階で、以下のような屋外での活動をシミュレーションしてみましょう。
- 電気:高圧洗浄機での掃除、DIYで使う電動工具、スマホの充電、クリスマスイルミネーション、防犯カメラ、将来の電気自動車(EV)の充電など
- 水:洗車、庭の花や木への水やり、夏の子どものプール遊び、窓や網戸の掃除、バーベキュー後の片付けなど
これらの用途に合わせて、使いやすい位置に防水仕様の「屋外コンセント」や、庭用の水道である「立水栓(りっすいせん)」を設置しましょう。
後から追加するのは大掛かりな工事になり費用も高くなるため、必ず最初の計画に含めておくことが重要です。
新築の外構工事費用を賢く抑える4つのテクニック
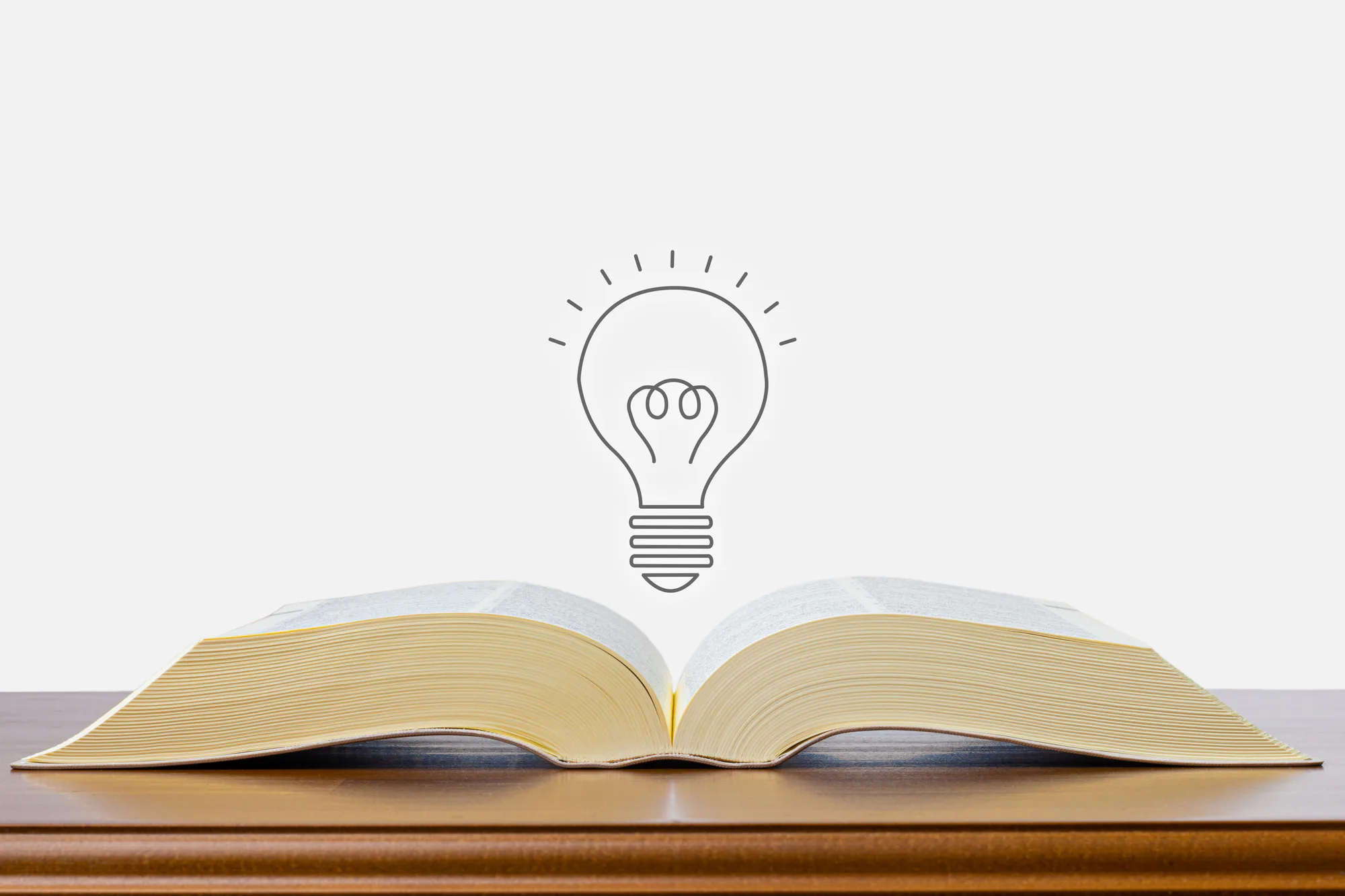
理想の外構を考え始めると、やりたいことが増えて予算が膨らみがちです。でも、少しでも費用を抑えて、理想を叶えたいですよね。
ここでは、予算内で満足度を最大限に高めるための、誰でも実践できる4つのコストダウンテクニックをご紹介します。
- 工事に優先順位をつけて予算を配分する
- DIYできる部分は自分でチャレンジする
- 使用する素材のグレードを見直す
- 複数の業者から「相見積もり」を取る
これらの賢いコストダウン方法を、一つずつ見ていきましょう。
工事に優先順位をつけて予算を配分する
外構工事で費用を抑えるための最も基本的な考え方は、「すべてを100点満点でやろうとしない」ことです。
まずは工事内容を「絶対に譲れないこと」と「できればやりたいこと」に仕分けしてみましょう。
例えば、「駐車場コンクリート」や「境界フェンス」は必須項目、「ウッドデッキ」や「植栽」は余裕があればやりたい項目、といった具合です。
予算を必須項目から割り振り、残りでやりたい項目を考える手順で、予算オーバーを防ぐことが出来ます。
今すぐには必要ないやりたい項目は、数年後に改めて工事する「二期工事」として計画するのも賢い選択です。
DIYできる部分は自分でチャレンジする
外構工事の費用には、材料費だけでなく、職人さんの人件費も大きな割合を占めます。
そこで、専門的な技術が不要な部分を自分たちでDIY(Do It Yourself)することで、その分の人件費を節約できます。
【DIYにおすすめの作業例】
- 砂利敷き:防草シートを敷き、その上に砂利をならす作業。
- 芝生貼り:天然芝のシートを敷き詰める作業。家族の良い思い出にもなります。
- 簡単な花壇づくり:ホームセンターで売っているレンガやブロックを並べるだけで作れます。
ただし、コンクリートを流し込んだり、ブロック塀を積んだりといった、安全性や耐久性が求められる工事は、必ずプロの業者に任せるようにしましょう。
使用する素材のグレードを見直す
外構工事は、使用する素材のグレードによって費用が大きく変動します。
費用を抑えるには、「お金をかける場所」と「コストを抑える場所」のメリハリをつけることが重要です。
例えば、お客様の目にも触れる玄関はこだわりの天然石を使い、普段あまり見えない家の裏手のフェンスは、安価なメッシュフェンスにするといった工夫です。
ウッドデッキも、高価なハードウッドではなく、比較的安価なソフトウッドや樹脂木を検討することで、コストを下げられます。
業者に「もう少し費用を抑えたいのですが」と相談すれば、似た雰囲気でより安価な代替素材を提案してくれることもあります。
複数の業者から「相見積もり」を取る
これは業者選びの章でも触れましたが、コストダウンの観点からも「相見積もり」は絶対に欠かせません。
同じ工事内容で見積もりを依頼しても、業者によってその金額は数十万円単位で変わってくることも珍しくないからです。
複数の業者から見積もりを取ることで、その工事の適正な価格帯を把握できます。また、他社の見積もりを提示することで価格交渉の材料になる場合もあります。
単に安い業者を選ぶのではなく、提案内容や保証、担当者との相性などを総合的に判断することが、コストパフォーマンスの高い、満足のいく工事につながります。
まとめ:計画的な準備で理想の新築外構を実現しよう

今回は、新築の外構工事について、計画を始めるタイミングから完成までの流れ、費用相場、そして後悔しないためのポイントまでを詳しく解説しました。
外構は「家のオマケ」ではなく、家族の暮らしを豊かにし、家の価値を大きく左右する重要な要素です。
そして、満足のいく外構工事を実現するための成功の鍵は、「早めの計画」と「信頼できる業者との出会い」の2点に集約されます。
この記事を参考に、まずはご家族で理想の暮らしや外構について話し合い、イメージを膨らませることから始めてみてください。
計画的に準備を進めることで、きっとあなたの新築の家をさらに輝かせる、理想の外構を実現できるはずです。
素敵なマイホームでの新しい生活が、最高の形でスタートできることを心から願っています。

蓑輪 達也
二級建築士|ハウスドゥ・ジャパン 売買建設企画部 西日本グループ グループ長 ハウスドゥ・ジャパンに新卒入社。施工管理職を経験後、現在は建築設計職を軸に施工管理・ビルディングマネジメントと活躍の場を多方面に広げています。 建築設計では、戸建てからホテル建築まで幅広くプロジェクトに携わっています。
KEYWORDS
