
家の買い替えを成功させたい!後悔しないためのタイミング・流れを網羅的に解説
家の買い替えは、人生のターニングポイントとなる大きな決断の一つです。 しかし、家の買い替えは、売却と購入を同時に進める必要があるため、資金計画や手続きが複雑になり、検討すべき事項も多岐にわたります。 ・今の住まいをできるだけ高く売却するには? ・住宅ローンは完済できる? ・新居の資金計画は問題ないか? ・売却と購入はどのように進めるべき? ・買い替えにはどのような費用や税金がかかる? これらを一般の方だけで適切に判断することは容易ではありません。そのため、信頼できる不動産会社のサポートを受けながら進めることが重要です。 この記事では、家の買い替えを成功させるために、知っておくべき基礎知識を網羅的に解説します。後悔しない家の買い替えを実現するために、ぜひ最後までご覧ください。
目次
家を買い替える理想的なタイミングは?

家の買い替えを成功させるには、今住んでいる家をできるだけ高く売却する必要があります。売却収入が多いほど、買い替えの資金計画に余裕が生まれるためです。
ここでは、高値で売却するうえで理想的なタイミングを解説します。
築11年~15年が一つの目安
一般的に、築年数が経過するほど家は売れにくくなり、売却期間が長期化したり、売却金額が下がる傾向です。
そのなかで、築11年~15年は、買い替えを検討する一つの目安となります。
下の表は、家の売却において、築年数別に中古マンションと中古戸建ての成約率※を表したものです。
※成約率:新規に登録された売却物件数に対して成約した件数を示したもの
築年数 | 中古マンション | 中古戸建て |
築0~5年 | 31.9% | 19.2% |
築6~10年 | 35.6% | 24.6% |
築11~15年 | 36.2% | 26.0% |
築16~20年 | 26.7% | 22.1% |
築21~25年 | 23.2% | 22.2% |
参照:公益社団法人 東日本不動産流通機構「築年数から見た 首都圏の不動産流通市場(2024年)」をもとに作成
上記を踏まえると、マンション・戸建てとも、築11~15年での成約率が最も高くなっています。特にマンションは、築15年を超えると成約率が10%近く下がります。
中古マンションの場合、新築から13~15年程度で大規模修繕工事を実施することが一般的です。
大規模修繕工事のタイミングで修繕積立金の値上げが行われることもあり、維持費が上がる前に売却を考える方が多いことが読み取れます。
また、中古戸建ては、築15~20年を過ぎると、屋根や外壁を含めたメンテナンスや修繕の必要になるケースが増えてきます。そのため、買主が購入後すぐに修繕しなければならない状態にならないよう、それより前に売却するほうが売りやすいといえるでしょう。
年間を通じて成約件数が多いのは、2月と3月
売り時を判断するうえでは、築年数のほか、売却時期も大切な要素になります。
以下の表は、令和5年3月~令和6年2月における月別の成約報告件数をまとめたものです。
マンション | 戸建て | |
令和5年3月 | 6,771件 | 5,796件 |
令和5年4月 | 5,888件 | 5,152件 |
令和5年5月 | 5,345件 | 5,260件 |
令和5年6月 | 6,174件 | 5,623件 |
令和5年7月 | 6,337件 | 5,938件 |
令和5年8月 | 4,618件 | 4,615件 |
令和5年9月 | 6,267件 | 5,784件 |
令和5年10月 | 6,448件 | 6,093件 |
令和5年11月 | 5,722件 | 5,366件 |
令和5年12月 | 5,799件 | 5,438件 |
令和6年1月 | 5,310件 | 4,831件 |
令和6年2月 | 6,509件 | 6,137件 |
参照:公益社団法人不動産流通推進センター「2024不動産業統計集(3月期改訂)」を元に作成
上記を見ると、マンション・戸建てともに2月と3月の成約件数が多い傾向が見られます。次いで、10月と7月も比較的動きが活発ですが、反対に、8月や1月は、成約件数が落ち込む傾向にあります。
2月や3月は、子どもの進学や転勤、異動に伴う引越し需要が集中する時期です。この時期に合わせた売却を進めることで、購入希望者が競合しやすく、より有利な条件で売却しやすくなります。
家の買い替えの流れ・手順

家の買い替えは、旧居の売却と新居の購入を並行して進めることになります。
それぞれの基本的な流れは、以下のとおりです。
旧居の売却の流れ | 新居の購入の流れ |
1.不動産会社に査定依頼 2.媒介契約の締結 3.売却活動をスタート 4.購入希望者と契約条件の調整 5.売買契約締結 6.引き渡し(引っ越し) | 1.資金計画の立案 2.情報収集・物件探し 3.購入申し込み・契約条件の調整 4.売買契約締結 5.住宅ローン本審査 6.引き渡し(引っ越し) |
ここでは、家を買い替える3つの手順について解説します。
- 家の買い替えの流れ|売却と購入を同時並行
- 家の買い替えの流れ|売り先行
- 家の買い替えの流れ|買い先行
家の買い替えの流れ|売却と購入を同時並行
旧居の売却と新居の購入を、同じタイミングで行う方法です。
具体的には、売却物件と購入物件の決済・引き渡しを、同日もしくは数日の猶予をもらって行います。
売却と購入を同時に進めるメリット・デメリット
メリット | デメリット |
・売却資金を購入資金に充てられる (ダブルローンの必要がない) ・仮住まいの費用や手間がかからない | ・スケジュール調整が難しい ・売り急いで売却金額が下がる可能性がある ・新居の購入に時間をかけられない場合がある |
売却と購入を同時に決済・引き渡しすることで、ダブルローンや仮住まいの必要がない状態で買い替えを進めることができます。
ダブルローンとは、現在の住宅ローンを返済しながら、新居のためのローンの借り入れをすることです。2本のローンを抱えるため、ある程度の金銭的負担が伴う方法です。
ただし、実際には、同時決済・引き渡しで進めることが難しいケースも少なくありません。
先に売却物件の購入者が見つかったものの新居が見つからない、あるいは、買いたい物件が決まっても売却の目途が立たないこともあります。
このような場合に、無理に同日決済で進めるようとすると、「売り急いで売却金額が下がる」「急いで新居を決めて後悔する」可能性があるため注意が必要です。
なお、売却と購入のタイミングが数日程度ずれる場合は、自宅の売却の売買契約に「引き渡し猶予の特約」を盛り込むと良いでしょう。
引き渡し猶予の特約とは、売却代金の決済後も、一定期間を定めて引き渡し日を伸ばしてもらう特約です。
決済が完了して所有権が買主に移った後も、一定期間そのまま住み続けられるため、新居の購入とのスケジュール調整がしやすくなります。
家の買い替えの流れ|売り先行
「売り先行」は、現在住んでいる家を売却した後に、新居の購入を進める流れです。
売り先行のメリット・デメリット
メリット | デメリット |
・資金計画が立てやすい ・時間をかけて売却活動を行える | ・仮住まいが必要となる場合がある ・新居探しに時間をかけられない可能性がある |
売り先行は、売却収入を新居の購入資金にあてられるため資金計画が立てやすい点が主なメリットです。
特に、自己資金が少なく資金計画に不安がある人には適した方法といえます。住宅ローンが残っていても売却資金を返済に充てられるため、ダブルローンを避けられます。
ただし、売却収入でローンを完済できない場合(いわゆるオーバーローン)、自己資金を準備するか「住み替えローン」の利用が必要になります。
※住み替えローンについては、後ほど詳しく解説します。
また、売り先行の場合、新居を購入するまでの期間に、仮住まいの家賃や引っ越し費用が余計にかかる可能性があるため、実家などに一時的に住める人には適した方法です。
家の買い替えの流れ|買い先行
「買い先行」は、新居を購入した後に、今住んでいる家を売却する手続きです。
買い先行のメリット・デメリット
メリット | デメリット |
・新居をじっくり探すことができる ・仮住まいの必要がない | ・資金計画に余裕がないと難しい ・二重ローンが発生する可能性がある |
買い先行は、新居探しに時間をかけられる点と、仮住まいの必要がない点がメリットです。
ただし、売却収入が確定していない状態で新居の購入を先行させるため、資金に余裕がなければ難しくなります。
住宅ローンを完済済み、あるいはローン残高が少ない、十分な自己資金がある方は進めやすい方法です。
家の買い替えを成功させるポイント

ここでは家の買い替えを成功させるポイントを3つ紹介します。
- 無理のない資金計画を立てる
- 買い替え特約を活用する
- 信頼できる不動産会社に相談する
無理のない資金計画を立てる
家の買い替えを成功させるには、無理のない資金計画が重要になります。
資金計画を立てる際は、次のポイントを確認しましょう。
- 住宅ローン残高(返済中の場合)
- 売却金額の見通し
- 買い替えのための自己資金
- 売却・購入それぞれにかかる諸費用
- 仮住まいや引越し費用
住宅ローン残高を含めて、買い替えにかかる費用をすべて洗い出し、それをもとに新居の購入資金を決めることが重要です。
ダブルローンや住み替えローンを活用する場合は、返済負担が大きくなりやすいため、完済するまでの返済計画をしっかりとシミュレーションする必要があります。
買い替え特約を活用する
売り先行で進める場合、「買い替え特約」の活用も検討しましょう。
買い替え特約とは、契約で定めた期限までに自宅を売却できなかった場合に、新居の売買契約を解除できる特約です。
新居の売買契約に買い替え特約を盛り込むことで、期限内に自宅を売却できない場合でも、違約金を支払うことなく契約の解除をすることが可能です。
ただし、買い替え特約は買主にとっては便利な特約ですが、売主は買主の売却が決まるまで不安定な立場におかれます。
そのため、中古住宅などの個人が売主の場合には特約を盛り込むことが難しく、新築一戸建てなど不動産会社が売主の物件で利用されることが多い傾向です。
信頼できる不動産会社に依頼する
家の買い替え時は、売却と購入、それぞれの資金計画やスケジュールを柔軟に調整しながら進める必要があります。購入だけ、あるいは売却だけの場合より、難易度は高くなります。
そのため、買い替えは同じ不動産会社で進めることが望ましく、依頼する不動産会社選びが重要になります。
買い替えの取扱い経験が豊富で、査定価格の妥当性、資金計画の立案、売却・購入それぞれのタイミング調整など、全体を見渡してサポートしてくれる不動産会社に相談できると安心です。
また、売却物件の購入希望者や希望条件に合う新居は、いつ見つかるかわかりません。物件によっては、想定以上に売却期間が長くなったり、売却金額が下がったりすることもあります。
状況の変化に合わせてフットワークよく、臨機応変に動いてくれる担当者を探しましょう。
家の買い替えで後悔しないための注意点

続いて、家の買い替えで後悔しないための注意点を3つ解説します。
- 相場とかけ離れた売り出し価格にしない
- 買い替えのスケジュールに余裕を持たせる
- 買取での売却を想定しておく
相場とかけ離れた売り出し価格にしない
できるだけ高く売りたいという気持ちはわかりますが、買い替えでは、「相場とかけ離れた売り出し価格にしない」ことが、スムーズな進行のカギになります。
家の買い替えでは、売却金額の見通しをもとに資金計画を立て、売却時期を想定しながら動くため、売却期間が長引くと計画が滞ってしまいます。
相場より高すぎる売り出し価格の物件は、販売当初の売れやすいタイミングを失いやすく、売却期間が長期化するリスクがあります。
相場に即した価格ならば比較検討の土台に乗せてもらえますが、同じ条件で価格が高すぎる場合は比べる対象から外されてしまう可能性が高いことを、よく理解したうえで進めましょう。
また、相場より高い売却収入を見込んで資金計画を立てることも危険です。実際の売却金額との差が大きいと、買い替えの計画そのものが崩れてしまいます。
そのため、複数の不動産会社の査定金額とその根拠を比較し、それをもとに無理なく住み替えを進められる売り出し価格を設定する必要があります。
買い替えのスケジュールに余裕を持たせる
買い替えでは、スケジュールに余裕を持たせることも重要なポイントです。
販売エリアや物件の状態、市場環境(金利動向など)によって販売期間は異なり、想定より長引く可能性もあります。短い期間内で売却と購入を同時に進めようとすると、結果的に新居の購入を急がざるを得なくなります。買い急いだことにより、新居の希望条件を妥協せざるを得なくなり、不満が残る買い替えになる可能性もあります。
売却と購入のスケジュール調整がしやすいよう、時間に余裕をもって買い替えを進めましょう。
買取による売却を想定しておく
物件の条件によっては、買主が見つからないこともあり得ます。万が一、自宅を売却できない場合に備えて、不動産会社による「買取」を想定しておくことも大切です。
買取とは、不動産会社が買主となって物件を買い取る方法です。
特に、需要が少ない物件は、一般の不動産市場で購入希望者を見つけることが難しい場合もあります。
一般的に、売れにくい物件の特徴は次のとおりです。
- 立地条件が悪い
- 築年数が古い
- 建物の状態が悪い
- 解体費用がかかる
- 管理費・修繕積立金が高い、など
このような買主を見つけることが難しい物件の場合、資金計画を立てる際には、買取を想定しておくと安心です。
買取の場合、一般の不動産市場での売却と異なり、不動産会社が取引相手であるため買主を探す必要がなく、現金化までのスピードが早い点などがメリットです。ただし、買取価格は、市場価格のおよそ6~8割と低くなります。
売れにくい条件の物件の場合、査定を依頼する段階で不動産会社のアドバイスを受けながら、買取になった場合の資金計画を想定しておくとより安心です。
家の買い替えでかかる費用

家の買い替えにおける、売却と購入それぞれにかかる諸費用について解説していきます。
- 旧居の売却にかかる諸費用
- 新居の購入にかかる諸費用
旧居の売却にかかる諸費用
以下の表は、家の売却にかかる諸費用をまとめたものです。
費用 | 内容 | 目安・計算方法 |
仲介手数料 | 売却を不動産会社に依頼したときの手数料 | 売買金額×3%+6万円(上限) ※売買金額が400万円超えの場合 |
印紙税 | 売買契約書に貼付する印紙代 | 売買金額によって異なる。 売買金額が1千万円超え5千万円以下の場合:1万円 ※軽減税率を適用した場合 |
登録免許税 | 抵当権の抹消にかかる税金 | 不動産1個につき1,000円 ※マンションの場合、土地・建物で2,000円 |
司法書士報酬 | 抵当権抹消登記を司法書士に依頼したときの費用 | 1万~3万円 |
住宅ローン繰り上げ返済の手数料 | 住宅ローンを完済するために金融機関へ支払う手数料 | 5,500~55,000円 ※金融機関・返済方法による |
なお、住宅ローンを既に完済している場合は、抵当権抹消のための登記費用や司法書士報酬、住宅ローンの繰り上げ返済の手数料はかかりません。
また、住み替え先が新築一戸建てや新築マンションで、不動産会社を介さずに直接売買契約を締結する場合は、仲介手数料は必要ありません。
新居の購入にかかる諸費用
続いて、以下の表は、新たに新居を購入するときにかかる諸費用をまとめたものです。
費用 | 内容 | 目安・計算方法 |
仲介手数料 | 購入を不動産会社を通じて行ったときにかかる手数料 ※直接買取の場合はかからない | 売買金額×3%+6万円(上限) ※売買金額が400万円超えの場合 |
印紙税 | 売買契約書に貼付する印紙代 | 売買金額によって異なる。 売買金額が1千万円超え5千万円以下の場合:1万円 ※軽減税率を適用した場合 |
登録免許税 | 所有権移転登記や抵当権設定登記にかかる税金 | 固定資産税評価額×税率 ※登記の種類によって税率は変わる |
司法書士費用 | 登記を司法書士に依頼したときにかかる費用 | 司法書士によって異なる |
住宅ローン事務手数料 | 住宅ローンを借り入れするために金融機関に支払う手数料・保証料 | 融資金額×2.2% ※金融機関によって異なる |
不動産取得税 | 土地や建物を購入したときにかかる都道府県税 | 固定資産税評価額×税率 ※ただし、一定の要件のもと軽減措置が受けられる |
火災保険 | 一括で支払う火災保険・地震保険料 | 補償内容や保険金額、保険会社によって異なる |
これらの諸費用以外にも、進め方や状況によってかかってくる費用を考慮しておくことも大切です。
売却を先行させる場合、新居が見つかり入居するまでの期間、仮住まいの費用や引越し費用がかかる可能性があります。
また、中古住宅への住み替えの場合、リフォームやハウスクリーニングなどの費用もかかることがあります。
ネットで情報を集めたり不動産会社に聞くなどして、どのような費用がかかりそうか把握しておけば、資金計画から大きく逸れる可能性も軽減されます。
ローンが残っていても家の買い替えできる「住み替えローン」とは?

住み替えローンとは、新居の購入費用に加えて、住宅ローンの残債分を借り入れできる商品です。
旧居の売却金額が住宅ローン残債金額に届かないこともあります。
家を売却するには、住宅ローンを完済し、担保として設定されている抵当権を抹消する必要があります。しかし、そのための資金を準備できないこともあるでしょう。
このようなときに、住宅ローンの返済資金に活用できるのが「住み替えローン」です。
たとえば、住宅ローンの残高が2,500万円あり、売却金額が2,000万円の場合、500万円の住宅ローンが残ります。
新居の購入資金が3,000万円だった場合、旧居の住宅ローン残債500万円を加えた3,500万円を住み替えローンで組むことができます。
住み替えローンのメリット・デメリット
メリット | デメリット |
・ローンが残ったまま新居を購入できる ・手元に資金を残せる ・二重ローンを避けられる | ・金融機関の審査が厳しい ・金利が高い傾向にある ・旧居の売却と新居の購入を同時に進める必要がある |
住み替えローンは、住宅ローンの残債があっても買い替えができる便利な商品ですが、借入金額が増えるため、通常の住宅ローンよりも借入のための審査が厳しくなります。
また、金融機関にもよりますが適用金利が高い傾向があるため、借り入れできた場合に無理なく返済していけるかを、しっかりと試算し、確認しておくことが重要です。
家の買い替え時に知っておきたい税金と特例

家の売却・購入を同時に行う買い替えでは、さまざまな税金を支払うことになりますが、活用できる特例も多くあります。
ここでは、住宅ローン控除も含めて、買い替え時に知っておきたい税金について解説していきます。
- 家を売って利益が出たときの税金
- 家の買い替えで活用できる3つの税制優遇措置とは
- 住宅ローン控除と併用できない特例
家を売って利益が出たときの税金
原則として、家を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、譲渡所得に対して所得税・住民税が課されます。
譲渡所得の計算方法は、以下のとおりです。
譲渡所得=譲渡価額-取得費-譲渡費用 |
それぞれの言葉の意味は次のとおりです。
・譲渡価格:買主から受け取る金額
・取得費:売却した家を購入した際にかかった費用
※土地・建物の購入費(減価償却分を差し引いたもの)や仲介手数料、印紙代など
・譲渡費用:家を売却する際にかかった費用
※仲介手数料や印紙代、登記費用など
譲渡所得がプラスになると税金の課税対象となりますが、居住用の家を売った場合に節税できる特例があります。
参照:国税庁「No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」
家の買い替えで活用できる3つの税制優遇措置とは?
家を買い替えるときに活用できる3つの特例を解説します。
- 3,000万円特別控除
- 軽減税率の特例
- 買い換え特例
3,000万円の特別控除の特例
「3,000万円特別控除」は、マイホームを売却して利益が出たとき、その譲渡所得から3,000万円を差し引くことができる制度です。
この制度は、物件の所有期間に関係なく利用可能であり、多くのケースで利用されています。
●控除額の計算方法(例)
売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いた利益が3,200万円の場合
・3,200万円(譲渡益)-3,000万円(控除)=200万円(課税対象)
※売却益が3,000万円以下であれば、全額が非課税となります
●適用されるための主な条件
- 自分が住んでいた建物、あるいはその敷地や借地権を売却すること
- 売却した年の前年および前々年に、同じ3,000万円控除またはマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例を受けていない
- 売却相手が親子や夫婦などの特別な関係でない
- 売却した年、その前年および前々年にマイホームの買換えや交換の特例を受けていない など
手続きと注意点
特例の適用するには、売却した翌年の確定申告期間(通常:2月16日~3月15日)に、税務署に申告書を提出する必要があります。申告のやり方も併せてチェックしておくと安心でしょう。
参照:国税庁「No.3302 マイホームを売ったときの特例」
マイホームを売ったときの軽減税率の特例
「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」は、売却した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えるマイホームを売却したときに、税率が軽減される制度です。
適用条件を満たすと、譲渡所得に対する税率は下記のようになります。
譲渡所得 | 税率 |
6,000万円以下の部分 | 10% |
6,000万円を超える部分 | 15%+600万円 |
※上記に併せ、令和19年までは、復興特別所得税として、所得税額の2.1%が課税されます
主な適用条件は、下記のとおりです。
- 自分が住んでいた建物、あるいは建物の敷地や借地権である
- 売却した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えている
- 売却年の前年・前々年にこの特例の適用を受けていない
- 売却した建物や土地についてマイホームの買換えや交換の特例など他の特例の適用を受けていない
- 売却先が親子や夫婦など「特別の関係がある人」ではない など
なお、この特例と「3,000万円控除」は併用して受けることも可能です。併用に伴う条件を事前に確認しておきましょう。
参照:国税庁「No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例」
マイホームの買い換え特例
「マイホーム買い換え特例」は、旧居を売却して譲渡益が出たとしても、その年の課税を一時的に先送りできる制度です。
通常であれば、マイホームを売却して利益が出ると、その年に譲渡所得税が課されます。しかしこの特例を使えば、買い替え後の新居を将来手放すときまで課税を先延ばしにすることができます。
これにより、買い替え時の税負担を大幅に軽減することが可能になります。
この制度を利用するための主な条件
- 居住期間・保有期間:売却した人の居住期間が10年以上、かつ売却した年の1月1日時点で売却した建物や土地の所有期間が10年を超えること
- 売却価格:1億円以下である
- 買い替える物件の条件:建物の床面積が50㎡以上、土地の面積が500㎡以下
- 売却期限:令和7年(2025年)12月31日
- 買い替えの期限:売却年の前年から翌年までの間(3年間)に買い替えること
- 売却した土地の前年から翌年までの間(3年間)に買い替えること
- 売却相手の条件:親子や配偶者など「特別の関係がある人」でないこと
この制度は課税が免除されるのではなく繰り延べられる点に注意が必要です。
最終的には、買い替えた住宅を売却したときに課税が行われるため、将来的な納税を見越して資金計画を考えることが大切です。
参照:国税庁「No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例
住宅ローン控除と併用できない特例
「住宅ローン控除」は、住宅ローンを利用してマイホームを購入したときに、年末時点の住宅ローン残高の0.7%を上限として所得税・住民税が還付される制度です。
控除期間は、13年間あるいは10年間で、購入する家によって異なります。
家の買い替え時にも、適用条件を満たせば住宅ローン控除を利用できます。
住宅ローン控除の主な適用条件
- 購入または新築後、6か月以内に居住している
- 床面積が50㎡以上であり、かつその過半数が居住用である(例外あり)
- 住宅ローンの返済期間が10年以上ある
- 生計を同じくする親族など特別な関係者からの購入ではない
- 年間所得が原則として2,000万円以下 など
ただし、先に紹介した以下の特例を適用する場合、住宅ローン控除は使えません。
- 3,000万円の特別控除
- 譲渡所得の軽減税率の特例
- マイホームの買い換え特例
そのため、住宅ローン控除で還付される税金と、特例による節税効果を比べて、どちらが有利になるかを見極めて判断する必要があります。
たとえば、売却益が大きく出る場合は「3,000万円控除」や「買い換え特例」の方が節税効果が高くなることもあります。
一方で、住宅ローンの借入金額が大きく、譲渡益が少なければ、住宅ローン控除による還付額の方が有利になることもあるでしょう。
金融機関のHPなど等で公開しているシュミュレーションを活用すれば、おおよその減税額がわ分かるため、参考にするのもおすすめです。
参照:国税庁「No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
家の買い替えなら新築デザイン住宅「SHIRO」
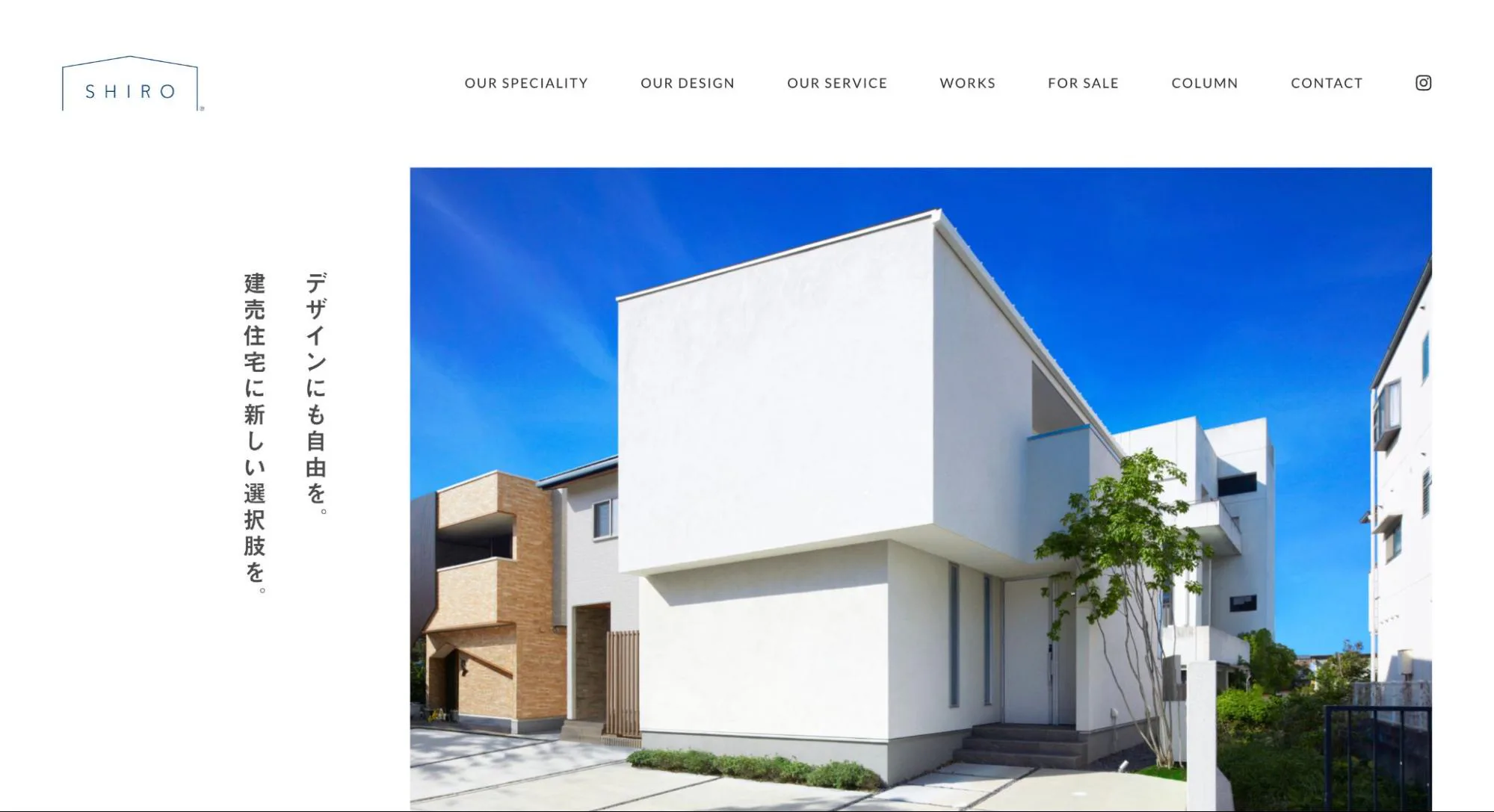
家を買い替える場合、仮住まいや二重ローンの負担を考えると、売却と購入を同時に進められるのが理想的ですが、実際にそのタイミングを合わせるのは容易ではありません。特に、個人が売主の中古物件へ住み替える場合、売主側も別の住まいへ引っ越す必要があるケースが多く、スケジュールや当事者間の調整が複雑になりやすい傾向があります。。
その点、不動産会社が売主である新築戸建て住宅は、完成済みであることが多く、未完成でも完成時期が明確なため、売却時期に合わせたスケジュール調整が比較的しやすくなります。
ハウスドゥ・ジャパンが提供する建売住宅ブランド「SHIRO」は、シンプルでありながら洗練された空間設計を追求した、新築デザイン住宅です。
「建売住宅に新しい選択肢を」というコンセプトのもと、過度な装飾を省き、空間に「余白」を持たせることで、住む人が自由にアレンジできる暮らしを実現しています。
土地と建物を一括で販売・管理しているため資金計画が立てやすく、買い替えにもおすすめの選択肢です。
家の買い替えは、人生で一度しかないであろう大きな決断です。資金計画やタイミング、進め方など、不動産取引に精通したスタッフが、あなたの状況に合わせた買い替えプランをご提案します。
まとめ:信頼できる不動産会社に相談して、家の買い替えを成功させよう

家の買い替えでは、その時の状況に応じた資金計画を立てて進めることが重要です。
- 住宅ローンが残っているか?
- 売却収入で住宅ローンを完済できそうか?
- 売却物件の需要はどれくらいか?
- 売却先はすぐ見つかりそうか?
- 諸費用や、買い替えに伴って発生する費用は?
- 買い替え後の住宅ローンの返済に無理はないか?
上記をしっかりと検討・確認し、最適な方法で進めていきましょう。
そのためには、信頼できる不動産会社のサポートが欠かせません。売却を依頼する際は、複数の不動産会社、担当者を慎重に比較し、信頼できる不動産会社に依頼しましょう。
「今の家のローンが残っていても大丈夫?」
「売却と購入、どちらを先に進めるべきだろうか?」
そのようなお悩みも、「SHIRO」の専門スタッフが、最適な買い替えプランをご一緒にご提案いたします。お気軽にご相談ください。

吉満 博
ゼネコン、ハウスメーカーで建築設計に従事後、自身の住宅購入をきっかけに不動産売買事業を始める。不動産の購入から売却まで出口戦略、資産性踏まえた長期の視点で不動産コンサルティング・売買仲介サービスを提供。これまでの実務経験を活かし、2023年から不動産・金融メディア中心にライターとしても活動。自身のサイトで不動産売買や住宅ローン等のお役立ち情報発信。
KEYWORDS


