
新築住宅の失敗事例14選!後悔しないための対策を徹底解説
新築住宅は、ほとんどの方にとって人生で一度しか経験しないであろう大きな買い物です。特に注文住宅においては、理想を反映できる反面、設計や設備・仕様の選択に慎重な判断が求められます。 理想の住まいを手に入れたはずが、住み始めてから「こんなはずじゃなかった……」と後悔するケースも少なくありません。 間取りや設備の選び方ひとつで暮らしやすさは大きく変わるため、失敗事例を参考に検討することも必要です。 また、いくら理想的な家ができたとしても、住宅ローンや建築費用などの資金計画の見通しが甘いと、購入後の生活が苦しくなりかねません。 そこで本記事では、新築住宅でありがちな14個の失敗事例を紹介するとともに、新築住宅で後悔しないための具体的な対策を解説していきます。 これから家を建てる方はもちろん、購入を検討中の方も、ぜひ参考にしてください。
目次
SHIRO新規分譲地情報のご案内
現在分譲エリア拡大中です。
いち早くSHIROの分譲地情報が欲しい方はこちらよりご登録ください。
新築住宅の失敗事例|間取り編

はじめに、新築住宅の間取りにおける失敗事例を5つご紹介します。
- 家事・生活動線の失敗
- 収納計画の失敗
- リビングの失敗
- 玄関の失敗
- イメージより普通の家になった失敗
家事・生活動線の失敗
家事・生活動線の失敗事例には、以下のようなものがあります。
- キッチンから洗濯・掃除への動線が悪い
- 洗濯機から物干し場へ移動が大変
- キッチンから冷蔵庫の設置場所が遠く、使いづらい
- 収納と使用場所が離れており、移動の負担が大きい
- 家族とのコミュニケーションが取りづらい
- 買い物をして帰った際の移動が非効率
キッチンから洗濯室や掃除用具収納が離れすぎていると、家事のたびに行き来しなければならず、作業効率に大きな影響を与えます。
また、キッチン内での調理スペースと冷蔵庫の配置が適切でないと、調理中に食材や調味料の出し入れがスムーズにできない不便さを、毎日感じることになってしまいます。
そのほか、洗濯機と物干し場が離れている場合、濡れた重い洗濯物を持って長距離を移動することになり、身体的にも大きな負担がかかります。
特に階段を使わなければ干し場に行けない場合、毎日の洗濯にかける労力は想像以上のものになることも。さらに、子どもの成長で洗濯物が増えれば、洗濯のための手間や負担は、さらに大きくなってしまいます。
生活動線上、玄関から直接階段で2階に上がれる間取りは便利ですが、家族がリビングを経由しないため、自然なコミュニケーションの機会が減る可能性があります。
しかし一方で、リビング内階段にするとコミュニケーションは増えるものの、リビングの空調が効きづらい場合もあるため、生活に合わせ取捨選択する必要があります。
また、在宅ワークスペースを家の端に設けた場合、静かで集中できるものの、子どもの様子がわからないことや、家族の存在を感じられず孤独を感じることがあります。
収納計画の失敗
収納計画の失敗には、大きく次の3つがあります。
- 収納スペースが足りない
- 収納の位置が悪く、使い勝手が悪い
- 収納の形状ミスで使いにくい
「収納スペースが足りない」というのは、とてもメジャーな失敗事例です。
生活を始めてから収納不足に気づき、追加で収納家具を設置したら空間が圧迫されてしまった…という失敗は多く見受けられます。
クローゼットが狭すぎると、衣類や荷物が収まりきらず、物があふれる状況になってしまうので注意が必要です。特に、季節ごとに入れ替える衣類や布団の量を考慮しないと、収納スペース不足で失敗する可能性が高くなります。
また、収納スペースが適切な場所にないと使い勝手が悪くなります。
例えば、玄関収納が不足すると、靴や傘、ベビーカーの置き場に困り、玄関が散らかる原因となってしまいます。
外から帰宅した際も、使った物や買い物したものを片づけておく収納の位置が悪いと、無駄な動きが増えてしまうでしょう。
さらに、キッチンパントリーの奥行きがありすぎると、奥にしまった食品の存在を忘れてしまい、賞味期限切れになることもあります。
最後に、収納の形状ミスで使いにくいケースです。
例として、ウォークインクローゼットのレイアウトをしっかりと考慮せずに設計すると、デッドスペースが生まれ、収納力が思ったよりも低くなることがあります。
また、床下収納を設置したけれど、「頻繁に開け閉めするのが面倒で、結局ほとんど使わなかった」という失敗例も。収納は、実際の使い勝手を考慮した計画が必要になります。
リビングの失敗
リビングの失敗例として、以下が挙げられます。
- リビングが広すぎて、冷暖房の効率が悪い・光熱費がかさむ
- 吹き抜けにした結果、冬場に暖房が効かず寒いリビングに
- エアコンの設置位置を考えず、効率的な空調管理ができない
- 広すぎて家具の配置が難しい・ソファやダイニングテーブルの配置が不自然
- 結局使わない無駄なスペースが生まれた
「とりあえずリビングは広く!」と設計した結果、空調の効率が悪くなるだけでなく、実際には使わない空間が生まれてしまったという失敗があります。
開放感を求めてリビングの天井部を吹き抜けにしたのはいいが、冬に暖気が上へ上へと逃げてしまい、光熱費が必要以上に高くなることもあります。
また、家具の配置まで深く考えないまま広く設計すると、ソファやダイニングテーブルの置き場が決まりにくく、不本意なデッドスペースが生まれがちです。
リビングを広くとることで魅力的な空間にすることもできますが、置こうとしている家具やソファセット等の配置、空調管理を考慮しながら、無駄なく間延びしないプランづくりをすることが大切です。
玄関の失敗
玄関のスペースを十分に確保しなかったことで、家族全員が同時に出入りできず、朝出かける際に混雑が発生するケースがあります。特に、子どもが多い家庭では、靴の履き替えや荷物の持ち運びで玄関が渋滞しやすくなるため、より注意が必要です。
また、玄関の収納計画が不十分だと、靴が玄関にあふれ、見た目が悪いだけでなく、スムーズな通行の妨げにもなるでしょう。
ベビーカーや傘の収納場所をしっかり確保できていないと、玄関スペースを圧迫し、使い勝手の悪さを日々感じることになってしまいます。
イメージより普通の家になった失敗
せっかく注文住宅を建てるのに、周囲の意見や無難なデザインを優先しつづけた結果、特徴のない普通の家になってしまった…という失敗事例があります。
また、予算内に収めることを重視しすぎた結果、普通の仕上がりになってしまうことも。例えば「吹き抜けや造作家具を検討していたものの予算オーバーで諦めた」などのケースがよく挙げられます。
そのほか、個性的な外観を希望して注文住宅にしたのに、施工会社の提案に流されて一般的なデザインになってしまい後悔するケースもあります。
ライフスタイルに合わせた家づくりをしたい、個性的なデザイン・間取りを取り入れたいという場合、より明確なイメージと資金計画を持って進めることが重要です。
新築住宅の失敗事例|設備・仕様編

次に、住宅設備や外内装材の仕様における失敗事例を3つご紹介します。
- 住宅設備の失敗
- 外壁・床材などの失敗
- スイッチやコンセントの失敗
住宅設備の失敗
住宅設備は、デザイン性だけでなく、機能性や作業効率も含めて選ばなければ失敗することがあります。
デザインにこだわってアイランドキッチンにしたものの、収納が少なく、思ったよりも作業動線が悪かった…というのも、その一例です。
アイランドキッチンは、調理中の油汚れが周囲に飛び散りやすいため掃除が大変になったり、壁がないためにリビングやダイニングから丸見えになる、などのネックがあります。そのため、常に清掃や整理整頓を意識しなければならず、心理的負担を感じることがある点に注意が必要です。
また、バスルームについても、広さや浴槽の向きによって快適性や使い勝手が悪くなり後悔することがあります。追加設備としてミストサウナや浴室テレビを付けたものの、ほとんど使わなかった…という失敗事例もよくあります。
そのほかにも「IoTを導入したら便利に暮らせそう!」と、スマートホーム機能を導入したものの、設定や操作が難しくてほとんど活用しなかった、というケースもあります。
外壁・床材などの失敗
外壁を明るい色にしたところ、汚れが目立ちやすく定期的な掃除が必要になった、という失敗例があります。
特に白やベージュ系の外壁は、雨だれや砂ぼこりの付着が目に見えてわかりやすいため、メンテナンスの手間が増えることが多い傾向です。
また、フローリング材も、高級感を重視して選んだ結果、傷がつきやすく後悔することがあります。無垢材のフローリングは見た目が美しい反面、傷や水濡れに弱く、こまめなメンテナンスが欠かせません。
外装材や内装材は住宅のデザイン面にも大きく影響しますが、耐久性やメンテナンスの必要性などを含めて考慮することも大切です。
スイッチやコンセントの失敗
スイッチやコンセントの失敗例として、以下があります。
- コンセントの数が少なく、家が延長コードだらけに
- コンセントの位置が悪く、家具の配置が制限される
- 生活動線上に照明のスイッチを配置すればよかった
- 充電スペースやキッチンのコンセントが足りず不便
コンセントの失敗例として見受けられるのが、スマホやタブレットの充電スペースを充分に確保しなかったため、リビングのコンセントをそれらが奪い合う状況などです。
キッチンでは、電気ケトルやミキサーなどの調理家電を考慮に入れなかったため、コンセントの数が足りないだけでなく、作業できるスペースも限られてしまったという失敗例もあります。
また、スイッチの位置を考慮せずに設計したため、照明のオンオフがすぐできずに「使いづらい」と感じることがあります。特に、寝室や廊下などでは、スイッチの位置が遠すぎると、夜間に不便さを感じることが少なくありません。
コンセントやスイッチの設計では、個数や場所、高さを、家具の配置や生活動線をイメージしながら決めていくことが大切です。
例えば「持っている掃除機は充電式なので収納場所にコンセントをつけておこう」という風に、実際の生活に即して考えていくことで、失敗の回避ができるでしょう。
新築住宅の失敗事例|立地・環境編

次に、立地や周辺環境で失敗した事例をご紹介します。
- 通勤・通学の負担が思ったより大きい
- 日当たりや風通しが悪い
- 周辺環境が悪い・合わない
通勤・通学の負担が思ったより大きい
土地を購入する前に、地図で確認した際は問題ないと感じたものの、実際に住んでみると駅までの道のりが予想以上に長く感じることがあります。特に、坂道や信号が多いと、想定よりも時間がかかるケースが少なくありません。
また、特に都市部では、朝のラッシュ時の混雑を考慮せず、通勤・通学が想定以上に大変だったという失敗もあります。
通勤や通学は毎日のことですので、時間や移動の負担は蓄積されていきます。家づくりでは、土地の周辺環境に目がいきがちですが、将来の子どもの進学なども含めて、通勤・通学の負担を考えることが重要です。
日当たりや風通しが悪い
購入時には日当たりの確認をしたつもりでも、実際に住んでみると、想像以上に陽が当たらなかったという失敗事例があります。
建物の配置上、隣地との境界までの距離が短い場合や、南側にマンションや高い建物がある場合は日が差し込みにくく、特に冬場は日照時間が短くなって室温も下がりやすくなります。
また、間取りを決める際に風の通り道を考慮しなかったため、夏場に風が抜けず、蒸し暑い空間になってしまうのも失敗の一例です。
特に窓が一方向にしかないと、気流の入口と出口がないために十分な換気ができず、エアコンに頼らざるを得なくなるケースも少なくありません。
周辺環境が悪い・合わない
周辺環境の失敗事例として、以下が挙げられます。
- 購入後に高層マンションが建ち、日当たり・景観が悪くなった
- 前面道路や近隣からの騒音が気になる
- 近くの公園や学校があり落ち着かない
- ゴミ捨て場の位置や管理状況を確認していなかった
- 灯り・人通りが少なく、夜になると不安を感じる
- スーパーや病院が少なく不便を感じる
周辺環境については、用途地域を確認して、将来どういった建物が建つ可能性がある地域なのかを知っておくことが重要です。
特に、近隣に大きな空き地がある場合、そこに大型施設やマンションが建つと、一気に周辺環境や雰囲気が変わる可能性があります。
大型施設が建設された場合、車の流れも変わります。周辺道路が常に混雑したり、子どもの交通安全を阻害する要因となることも理解しておきましょう。
別の失敗事例として、昼間に視察して静かだったからと購入し、住み始めてから別時間帯の騒音に悩まされることもあります。検討中の地域は、あらゆる時間帯の状況を確認しにいくことで、失敗の予防が可能でしょう。
例えば大きめの公園が近いと子育てには便利ですが、休日も朝から騒がしい可能性があります。音に敏感なタイプの方は特に「失敗した」と感じる環境になり得ます。
新築住宅の失敗事例|資金計画・住宅ローン編

最後に、新築住宅の資金計画や住宅ローン選びでの失敗事例をご紹介します。
- 住宅ローン返済以外の維持費が家計を圧迫
- 諸費用の見落としや追加費用で予算オーバー
- ボーナス返済の割合が大きすぎて失敗
住宅ローン返済以外の維持費が家計を圧迫
住宅ローン返済以外の維持費をしっかりと考慮していないと、思った以上に家計を圧迫してしまう失敗事例があります。
維持費として、固定資産税や火災保険料、将来の修繕費の積み立てなどが必要なほか、賃貸物件から一戸建てに変わったことで光熱費が上がるケースもあります。
また、採用する建築資材や立地条件によってメンテナンス費用は変わりますが、ほとんどの場合は新築から10年、15年程度になると、外壁や屋根を含めてまとまった修繕費用が必要です。
子どもの成長に伴って生活費や教育費の負担が重くなることや、将来の老後資金の積み立てなども踏まえて、資金計画を考えることが大切です。
諸費用の見落としや追加費用で予算オーバー
注文住宅の資金計画では、土地取得費、建物建築費以外の諸費用をしっかりと見積もらないと、予算オーバーで失敗してしまう可能性があります。
特に土地から取得する場合、土地取得に伴う仲介手数料や印紙代、登記費用のほか、地盤調査費用や土地の状況によっては地盤改良費が発生することがあります。このような費用は、いわゆる「ちりつも」で、最後に見返すと想定外の出費になっていることも。
また、建物の間取りプランや仕様、設備をしっかり確定したうえで契約することが大切です。
しっかり決めない状態で契約してしまうと、後にオプション追加や仕様変更を重ねることになり、総費用が当初の予定を大幅に超えてしまうケースがあるためです。
ボーナス返済の割合が大きすぎて失敗
さらに失敗事例の中には、ボーナス返済を前提にローンを組んだが、収入減で支払いが厳しくなってしまった…というケースがあります。
ボーナスは、毎月の給与よりも、勤務先の業績や経済環境の変化に左右されやすいものです。配置転換などで業績連動型の報酬体系に変わるケースもあるでしょう。
仮にボーナスでローンを返済できたとしても、大半がその支払いに消えてしまい、必要な貯蓄ができずに趣味や家族旅行もあきらめざるを得ないこともあります。
毎月の返済額を抑えようとして、安易にボーナス返済の割合を増やすことは、あまりオススメできません。余暇や将来のための貯蓄も考慮したうえで、慎重に判断しなければなりません。
新築住宅で失敗しないための対策

では、新築住宅で失敗しないためにはどういった点に気をつければよいのでしょうか。それぞれの対策を解説します。
間取りで失敗しないための対策
家事・生活動線を考えるうえでは、実際の動きをイメージしながら、キッチンや洗濯機、物干し場、収納などの位置関係を決めることが大切です。
キッチンの動線が長すぎると作業効率が悪くなり、掃除の手間も増えるため、適度な広さに収めることが必要です。
また、そのほかの部屋に関しても、子どもの成長や独立を考慮し、長期的な視点でライフスタイルの変化に適応できる間取りを考えることが重要になります。
収納計画は、一か所の大きな収納におさめようとするのではなく、基本的に「使う場所の近く」に収納を設置すると日々の暮らしがスムーズになります。
ウォークインクローゼットや玄関収納、パントリーに必要な収納量をしっかりと検証し、適切な大きさのものを適切な場所に配置することで、家全体が片付きやすくなります。
1か所に大きな収納を設ける場合は、むやみに奥行きを深くしすぎず、収納力だけでなく出し入れの利便性にも注目しましょう。もちろん、無駄なスペースを減らす工夫も欠かせません。
また、リビングは広すぎると冷暖房費がかさむため、断熱性能の高い建材や気密性の高い窓、床暖房の採用も検討してみましょう。
吹き抜けのリビング階段では、シーリングファンを設置することで、暖気が上部に溜まらずに部屋全体にいきわたり、効率的な空調が可能になります。
さらに、玄関は、混雑を避けるためにも適度な広さを確保し、靴や傘、アウトドア用品などの必要な収納量をシミュレーションすることが重要です。棚を可動式にすることで、必要に応じて収納のレイアウトを変えられ、使い勝手が向上します。
設備・仕様で失敗しないための対策
住宅設備や外壁・内装の仕様選びでは、見た目の印象や最新のトレンドに流されず、実際の使い勝手やメンテナンス性を考慮することが重要です。
特にキッチンや浴室、トイレといった水回り設備は、カタログ上のスペックだけで判断するのではなく、ショールームで実物の規模感を見たり、実際に操作することが必要です。
そうすることで、日常生活で必要な機能や利便性を実感しやすく、「不要な機能を追加してしまった」「使いづらい」などの失敗が減ります。
また、外壁や内装材は、デザイン性だけでなく耐久性や手入れのしやすさも考えて選ぶことが重要です。特に外壁材は、汚れが付きにくくメンテナンス頻度が少ないものを選ぶと、将来の維持費を抑えることにつながります。
内装材は、フローリングや壁紙の質感・色味がカタログと実物では異なることがあるため、サンプルを取り寄せて実際の光の下で確認するとよいでしょう。
床材や壁紙は面積の広い部分でもあるため、「思い描いていたものと違うな」と感じた場合の精神的なダメージも大きくなります。色や手触りなどをしっかり確認し、自分のイメージに近いものを見つけましょう。
さらに、流行に左右されず、長期的な視点で仕様を決めることも失敗を防ぐポイントのひとつです。特注仕様の設備は、既製品よりも交換時にコストがかかる傾向にあるため、将来的な修理やメンテナンスのしやすさも考慮すると安心です。
立地・周辺環境で失敗しないための対策
まず、通勤・通学の利便性を確認するため、実際に朝の時間帯に駅やバス停まで歩き、所要時間や交通の便をチェックしましょう。
乗り換えのしやすさや公共交通機関の運行本数、乗っている人の多さなども考慮し、移動の負担がどの程度かをきちんと確認することが重要です。
次に、日当たりや風通しの良さを確保するため、周辺に高い建物がある場合は、ハウスメーカーに日照時間のシミュレーションを依頼してみましょう。
冬場の日照時間や夏場の直射日光の影響を考慮し、窓の位置や間取りを工夫することで、快適な住環境を実現できます。不安がある場合は、設計士に相談すれば、それに即したプランを提案してくれるでしょう。
また、将来的な周辺環境の変化も見落としてはいけません。近隣に工場や繁華街、大きな空き地など、騒音や臭いの原因となる施設や将来の建築候補地がないか確認することが大切です。
さらに、市区町村の開発計画を調べ、今後の再開発や新たな施設の建設予定がないかを把握しておくと安心ですよ。
これらのポイントを踏まえ、実際に現地を訪れ、昼夜や平日・休日の環境の違いもチェックしながら慎重に立地選びを進めましょう。
資金計画・住宅ローンで失敗しないための対策
お金の面での失敗を避けるためにも、自己資金と無理のない借入金額から住宅購入予算を設定することが重要です。
資金計画においては、土地購入資金と建物建築費のほかに、諸費用や地盤改良費などの追加で発生する可能性のある費用もしっかりと調べて把握しておきましょう。
また、住宅ローンの返済額は、返済負担率を目安に考えるのも一つの方法です。
返済負担率とは、年収に対して1年間の住宅ローンの返済額(諸費用含む)が占める割合です。無理のない返済負担率の目安は、20~25%といわれています。
また、住宅ローンで変動金利を選ぶときは、将来的な金利上昇のリスクを踏まえ、事前に家計への影響をシミュレーションしておくとよいでしょう。
金融機関にお願いすると返済シミュレーションを作成してくれますし、ウェブ上のシミュレーションを使って計算することも可能です。家計との兼ね合いについて、ファイナンシャルプランナーなどのお金のプロに相談するのも良い対策です。
資金計画や住宅ローン選びは、単に借入可能な金額で決めるのではなく、将来のリスクや家計を見据えながら、慎重に判断することが重要です。
デザイン住宅「SHIRO」で後悔のないマイホーム購入を
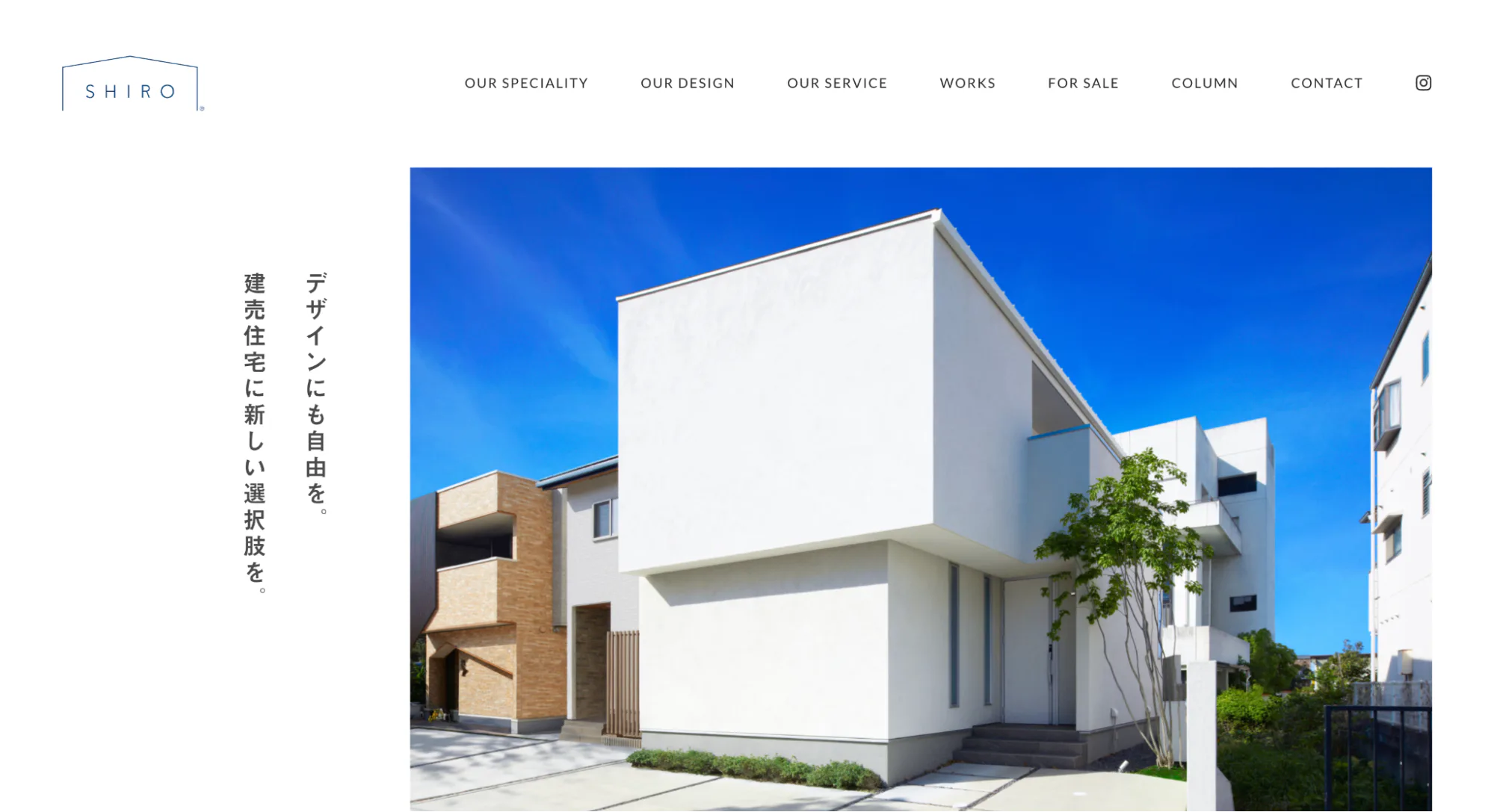
ハウスドゥ・ジャパンが提供するデザイン住宅「SHIRO」は、デザイン性と経済性を両立させた建売住宅ブランドです。
白を基調としたシンプルかつ洗練されたデザインと余白を活かした空間設計は、従来の住宅と同じ広さでもゆとりを感じさせ、その空間的な余白に住む人の個性を反映できる住まいとなっています。
これまで約1,600棟の建売販売で培ったノウハウをもとに、敷地の条件に合わせ、無駄のない快適で機能的な間取りを提案しています。
また、建築後の維持費やメンテナンスについて、長期保証制度と充実したメンテナンス体制がある点も特徴の一つです。「20年の地盤品質保証」「10年のシロアリ保証」など、長く安心して暮らせるようサポートさせていただきます。
さらに「SHIRO」では、土地と建物を一括で管理・販売するため資金計画が立てやすく、工期を短縮することでコストを抑えやすくなっています。原則として仲介手数料が発生しない仕組みを採用し、諸費用を抑えた明瞭な価格設定が特徴です。
まとめ:新築住宅の失敗事例をもとに対策をまとめよう

新築住宅の失敗は、間取り・設備・資金計画・立地選びなど、さまざまな要因から生じます。
失敗を防ぐには、家族構成やライフスタイルをもとに、具体的に生活をイメージしながらマイホームの計画を進めることが重要です。
その際、子どもの成長やライフスタイルの変化などを踏まえて、長期的な視点で考えるとよいでしょう。
また、無理のない資金計画を立てるためにも、家づくりに求める条件、優先順位を明確にすることが大切です。自分にとって必要な間取り、広さ、機能・仕様は何かをしっかりと把握することで、失敗の可能性は少なくなります。
ハウスドゥ・ジャパンが提供するデザイン住宅「SHIRO」は、建売住宅でありながら注文住宅に引けをとらないデザイン性と間取りを兼ね備えた住宅ブランドです。
専門のスタッフが、お客様一人ひとりに最適なご提案をさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。

吉満 博
ゼネコン、ハウスメーカーで建築設計に従事後、自身の住宅購入をきっかけに不動産売買事業を始める。不動産の購入から売却まで出口戦略、資産性踏まえた長期の視点で不動産コンサルティング・売買仲介サービスを提供。これまでの実務経験を活かし、2023年から不動産・金融メディア中心にライターとしても活動。自身のサイトで不動産売買や住宅ローン等のお役立ち情報発信。
SHIRO新規分譲地情報のご案内
現在分譲エリア拡大中です。
いち早くSHIROの分譲地情報が欲しい方はこちらよりご登録ください。
KEYWORDS



